| 2.都市施設基本計画 |
| 2.1 道路の整備方針 |
| (1)道路整備の考え方 |
道路整備は、広域的な交流を活力ある地域の発展につなげていくため、面的な土地利用との一体的な整備を図ります。
広域的には、東京方面や県際の周辺都市等との広域的なネットワークの形成によって、本町の発展・成長につながるような道路整備を図ります。特に第二東名自動車道の早期建設と開放型休憩施設の設置や近隣市町村と歩調を合わせたインターチェンジ等の設置は、本町の都市構造を大きく変える可能性を持っていることから、その実現に向けた積極的な取り組みを行っていきます。また長期的には、本町と南足柄市との間の円滑な交通を実現する足柄道路の整備を検討します。
町内の道路整備においては、国道246号、138号等の広域的な幹線道路と有機的にネットワークするように、本町の地域間、各種都市拠点間等を連絡する幹線道路を位置づけ、未整備である都市計画道路の整備推進とともに、今後の開発等に併せた新たな路線の計画決定や変更を図ります。また休憩施設については、国道246号、138号における道の駅の整備促進を、関係機関とともに推進していきます。
道路沿道については生活道路を中心として緑化等にも十分配慮した環境整備を行います。歩行空間の確保については段差の解消、スロープ、点字ブロックの設置など子供からお年寄り、障害者が安心して通行することの出来るユニバーサルデザイン(注)に基づいた整備を積極的に推進します。小中学校の通学路については、児童、生徒が安心して通行できるような道路整備を図ります。
また、こうした道路整備に際しては、主体となる利用者(幹線道路を利用する通過交通、生活道路を利用する居住者、通学路を利用する児童・生徒等)を明確にした上で、需要に応じた道路整備、市街地内の歩行空間ネットワークの構築を図ります。
街路樹については地域特性に応じて道路路線毎に街路樹を変化させるなどにより、特色ある道路整備を図ります。 |
|
ユニバーサルデザイン(注):
「すべての人のためのデザイン(構想、計画、設計)」という意味です。年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、建物・施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方です。 |
|
| (2)交通軸の形成 |
① 広域的な道路軸
② 隣接市町村及び地域間・拠点間を結ぶ道路軸
③ その他の生活軸 |
| (3)道路の配置計画 |
| 表 交通軸別の道路の一覧 |
|
交通軸
|
具体的な道路名称
|
道路機能
|
|
広域的な道路
|
●自動車専用道路
|
|
|
東名高速道路
|
国の東西骨格を担う高規格幹線道路
|
|
第二東名自動車道
|
国の東西骨格を担う高規格幹線道路
|
|
東富士五湖道路
|
国道138号に連絡して山梨県を結ぶ有料道路
|
|
●一般道路
|
|
|
国道246号
|
首都圏(東京都、神奈川県)と沼津市とを結ぶ一般国道
|
|
国道138号
(都)御殿場須走線
|
神奈川県箱根町と山梨県富士吉田市とを結ぶ一般国道
|
|
隣接市町村及び地域間・拠点間を結ぶ道路
|
●一般道路
|
|
|
(県)沼津小山線
|
沼津市と小山町を結ぶ一般県道
|
|
(主)御殿場大井線
|
御殿場市から小山町を経由して神奈川県を結ぶ主要地方道
|
|
(県)足柄峠線
|
足柄峠に連絡する一般県道
|
|
(県)山中湖小山線
|
山梨県の山中湖村と小山町を結ぶ一般県道
|
|
(県)須走小山線
|
須走地域と小山地域を結ぶ一般県道
|
|
(県)足柄停車場富士公園線
|
足柄駅から富士山頂に向かう一般県道
|
|
(都)原向中日向線
|
小山地域から北郷地域を経由して富士スピードウェイを結ぶ
都市計画道路
|
|
(都)茱萸沢棚頭線
|
御殿場市と北郷地域を結ぶ都市計画道路
|
|
(町)上野大御神線
|
富士スピードウェイの南側に伸びる町道
|
|
(町)3866号線
|
東富士リサーチパーク内を東西に走る町道
|
|
(町)用沢大御神線
|
冨士霊園と用沢地区を結ぶ町道
|
|
(都)打越用沢線
|
(都)竹之下中島線と(都)茱萸沢棚頭線を結ぶ都市計画道路
|
|
(都)吉久保阿多野線
|
(都)原向中日向線と(都)打越用沢線を結ぶ都市計画道路
|
|
(都)竹之下中島線
|
足柄駅から国道246号中島I.Cを結ぶ都市計画道路
|
|
(都)足柄三保線
|
足柄駅前土地区画整理事業地内の都市計画道路
|
|
(県)駿河小山停車場
|
駿河小山駅と中心市街地とを結ぶ一般県道
|
|
(県)竹之下小山線
|
小山地域と足柄地域とを結ぶ一般県道
|
|
| (都)は都市計画道路、(主)は主要地方道、(県)は一般県道を示している。 |
| (4)都市計画道路の見直し |
| 道路の配置計画に基づき、関係機関とともに、現在計画決定している都市計画道路の見直しを行っていきます。 |

(図をクリックすると拡大されます。)
図 将来骨格道路網図 |
|
| 2.2 公共交通機関の整備方針 |
| (1)基本的考え方 |
| 鉄道・バスなどの公共交通機関の充実を図ることは、交通弱者の移動手段を確保し、利便性の高い都市生活を営む上で欠かすことのできないものです。特に高齢化が進むこれからのまちづくりにおいては、公共交通機関の重要性がますます高まってくるものと考えられます。このため、鉄道、バス等の公共交通機関の整備充実に向けた積極的な取り組みを図ります。 |
| (2)整備方針 |
| ① 鉄道及び駅前広場整備 |
JR御殿場線の利便性を高めるために、JR東海及び小田急電鉄など関係機関に、電車運行本数の増加、観光列車の運行などについての要請を引き続き行っていきます。また、長期的には、伊豆箱根鉄道大雄山線の延伸を関係機関に要請していきます。
また駿河小山駅、足柄駅は、交通結節点として観光客、ハイキング客等の一時的滞留者の安全性と快適性が求められるほか、観光コースの発着点ともなっていることから、駅舎改築、情報提供、休憩施設の設置、バス、タクシー等の滞留空間の設置など駅ターミナル機能の拡充を図ります。 |
| ② バス機能の充実 |
現在、バス交通は町内の市街地、集落地及び主要拠点間を結んで運行されていますが、モータリゼーションの発展とともに、利用者の減少が進んできています。しかし高齢化社会の一層の進展が予想される今後、交通弱者である高齢者の足として、バス交通の必要性はますます高まってくるものと考えられることから、IT技術を活用したデマンドバス(注)の運行など、バス需要に的確に応えることのできる方策を交通事業者と協力して検討します。
また施設においては、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえながら、停車施設の整備などについて、交通事業者と協力して検討を進めます。将来的には、バス事業の自由化に配慮しながら、集落地や各種拠点間を結ぶ交通網の確立を推進していきます。
また、健康福祉会館、生涯学習センター、町役場、各支所を結んでいる巡回バスについては、その機能充実を図っていきます。 |
|
| デマンドバス(注): |
基本路線の外に迂回ルートを設定し、利用者がいる場合に迂回ルートを走行するなど、デマンド(需要)に応じて弾力的なサービスを行うバスです。 |
|
| 2.3 公園緑地の整備方針 |
| (1)基本的考え方 |
| 本町を取り巻く豊かな自然環境を再認識し、環境保全、レクリエーション、防災、景観形成のそれぞれの観点から緑を捉え、その維持・保全及び緑の創出に向けた施策の立案に向け、検討していきます。 |
| (2)公園緑地の配置方針 |
| ① 自然的、農業的土地利用ゾーン |
自然環境保全ゾーンにおいては、自然環境を維持し、将来にわたって継承していくために、緑の保全のルールを確立していきます。特に市街地を取り囲む山々から市街地近辺まで連続する森林については、市街地を取り囲む形で緑豊かな都市の骨格を形成します。また市街化調整区域では、無秩序な開発による樹林地の減少が著しいところもあることから、地域環境の向上に資する貴重な緑地として位置づけ、その保全を図ります。
市街地及びその周辺部においては、市街地の背景を構成する稜線や市街地に隣接する樹林地等を地域のランドマーク、シンボルとなる緑地として位置づけます。また水辺空間や河川等の緑地は、積極的に面的整備計画の中に取り込んで、緑の保全・育成を図ります。こうして確保した緑地を相互につなぎ、系統的な緑の連続性を確保し、河川及び河川沿いの樹林地等の緑地と基幹公園を有機的に連絡していきます。
農業緑地形成ゾーンにおいては、広大な田園景観を形成する大規模農地を保全し、宅地開発を抑制するとともに、集落地の生垣や庭木、水路の石護岸など身近にある緑については、地域の修景に寄与する緑地として保全していきます。
また、中島八重桐の池など地域の固有資源となる自然・歴史環境を活用した特色ある公園の整備を図ります。 |
| ② 都市的土地利用ゾーン |
現在、本町には「小山町都市公園条例(平成9年3月19日)」が制定されており、土地区画整理事業や開発行為によって整備された公園が、この条例に基づいて都市公園・緑地に定められています。今後とも本条例の適切な運用を図ると共に、都市施設としての都市計画公園の計画決定及び整備に向けた検討を引き続き行います。
都市公園としては、公園の利用目的に応じて、防災上の視点を踏まえながら、小規模公園やポケットパークなど、だれもが気軽に憩うことのできる身近な公園の適正配置を推進します。
また、街路樹や生垣の設置、公共施設、工業団地内等の緑化等、都市施設や建物整備にあたっての緑の整備、緑地を相互に連絡する緑道の配置及び河川敷緑地の活用等による緑地のネットワークの形成を図ります。特に、鮎沢川、佐野川、須川等の河川緑地及び幹線道路沿道の街路樹を主体とする緑化空間を軸として、公園・緑地等を有機的に結びつけるネットワークを形成します。
市街地内及びその周辺斜面部に数多く分布する埋蔵文化財等については、学術上貴重なだけでなく、周辺の緑地とともに、地域の個性を形成する緑地でもあることから、緑地保全地区等の指定の検討を行います。また、市街地には境内樹林を有する寺社・仏閣が数多く分布しており、「冨士浅間神社のハルニレ」等、境内樹林が天然記念物に指定されているものもあることから、こうした拠点となる緑と風土に根ざした屋敷林等の保全及びそれぞれの資源のネットワークの形成を図ります。 |
|
| 表 「小山町都市公園条例」に基づき指定されている都市公園・緑地の一覧 |
| 設置年度 |
名 称 |
区分 |
面積(㎡) |
備 考 |
| S60 |
下谷緑地 |
緑地 |
1,671 |
下谷土地区画整理事業による。 |
| S62 |
棚頭第一公園 |
公園 |
4,906 |
富士小山工業団地整備事業による。県土地開発公社より帰属。 |
| S62 |
棚頭第二公園 |
公園 |
1,367 |
富士小山工業団地整備事業による。県土地開発公社より帰属。 |
| S61 |
佐野川公園 |
公園 |
613 |
用沢佐野川土地区画整理事業による。 |
| H1 |
一色みどりのひろば |
公園 |
476 |
一色平沢土地区画整理事業による。 |
| H1 |
一色いこいのひろば |
公園 |
337 |
一色平沢土地区画整理事業による。 |
| S62 |
須走希望ヶ丘公園 |
公園 |
120 |
開発行為(須走希望ヶ丘団地)による。個人より帰属。 |
| H2 |
湯船原第一公園 |
公園 |
1,000 |
開発行為(富士小山ハイテクパーク)による。企業より帰属。 |
| H2 |
湯船原第二公園 |
公園 |
7,479 |
開発行為(富士小山ハイテクパーク)による。企業より帰属。 |
| H3 |
宿さくら公園 |
公園 |
618 |
合土ヶ久保土地区画整理事業による。 |
| H3 |
わさび平公園 |
公園 |
2,235 |
開発行為(富士小山わさび平コーポレートリサーチ)による。企業より帰属。 |
| H7 |
富士見平公園 |
公園 |
409 |
下原団地造成事業による。県住宅供給公社より帰属。 |
| H8 |
みどり友情のひろば |
公園 |
565 |
緑ヶ丘団地造成事業による。県住宅供給公社より帰属。 |
| H8 |
足柄みずべ公園 |
公園 |
2,310 |
足柄駅前土地区画整理事業による。 |
| H10 |
音渕公園 |
公園 |
913 |
富士紡績㈱からの買収による。 |
| H13 |
小山公園 |
公園 |
1,717 |
防衛補助事業による。 |
| 合 計 |
26,736 |
|
|
| 2.4 下水道の整備方針 |
下水道事業は、基本的に、平成2年度に策定した小山町下水道基本構想に基づいて事業を推進しますが、生活環境の向上を早期に図るため、当面公共下水道の整備が見込めない区域などについては、合併処理浄化槽の設置を推進します。今後は、新規開発事業等への対応も踏まえ、下水道計画を見直し、公共下水道事業や農業集落排水事業を適正に推進していきます。
また、公共下水道事業や農業集落排水事業の区域外では、合併浄化槽、コミュニティプラントの設置等によって、河川の水質浄化を進めていきます。
さらにPR活動等によって、河川の水質浄化に対する町民意識の向上を図ります。 |
| 2.5 河川の整備方針 |
河川整備にあたっては、治水対策に加えて、利水、親水の側面から整備のあり方を検討し、足柄駅前土地区画整理事業周辺や健康福祉会館周辺における護岸改修のように、親水空間としての整備を図っていきます。特に、市街地内を流下する鮎沢川、佐野川、須川等の河川空間は、緑地としても貴重な空間であることから、河川沿いの遊歩道やジョギングコースの設置、親水公園の設置など、ふれあいの場の創出について検討し、市街地内の貴重なオープンスペースとして機能させます。
また下水道整備による河川の水質向上に努めるとともに、環境に配慮した工法の導入を推進し、魚の群れる河川環境を取り戻します。 |
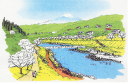
(画像をクリックすると拡大されます)
町内を流下する河川の親水性の向上 |
|
![]()